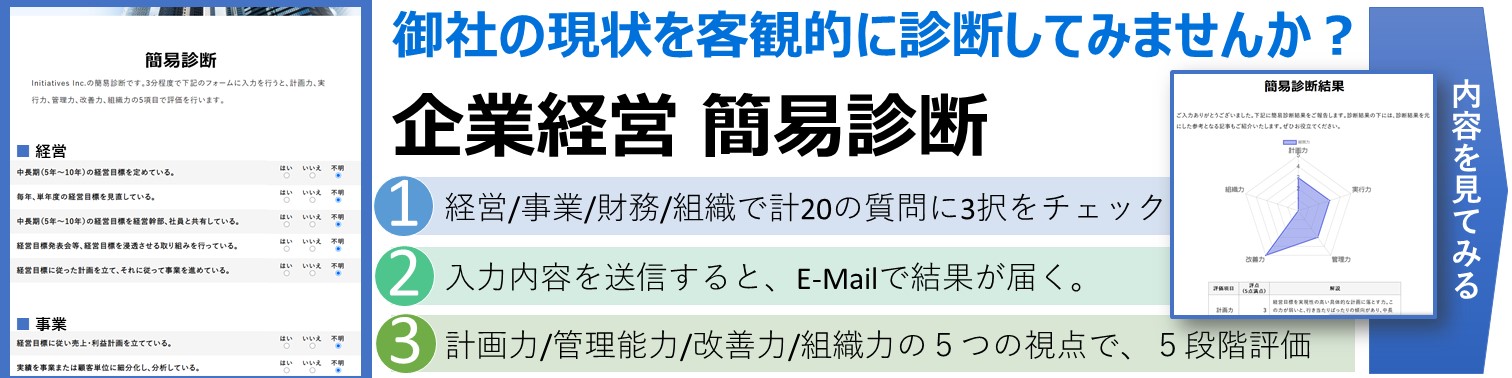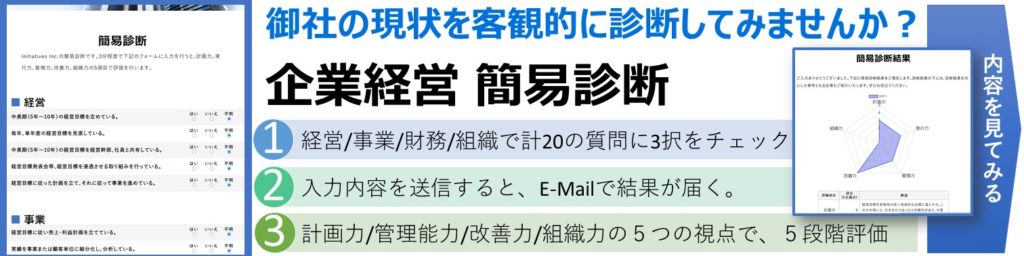要点
- 質問する
- 褒める
- 表彰する
- 計画発表会
- 1対1面談
経営理念を浸透させるにはどうしたら良いのだろうか。
経営理念を浸透させる方法として、朝礼などで唱和させる方法もある。しかし、経営者側から一方的に発信した場合、浸透効果は薄いと言われている。そこで日常業務の中で機を見て経営者の考え方を社員に伝えることが必要となる。
製造業ではQC活動や改善活動などで改めて業務を見直す機会を設けていることが多い。こうした業務の一環として経営理念を考える機会があれば一番良い。例えば、理念に沿った製品を造る、活動を行うなどが出来れば一番よいであろう。
SDGsを理念で謳う企業は、SDGsに則った製品・商品を扱うことが出来れば、経営理念は浸透しやすい。
感謝を大事にしているある会社では「ありがとうカード」を廊下に張り出しているところもある。「ありがとうカード」はある社員が他の社員からしてもらった良いことをカードなどに記載して投函し、それを廊下に貼り出すなどして発表する活動である。ポイントは、「ありがとうカード」をたくさんもらった社員の評価が高いのではなく、「ありがとうカード」をたくさん投函した社員の評価が高いということである。
通常業務時間内の全社活動なので、社員への浸透度は高い。
ここではこうした機会以外に経営理念を浸透させる方法について述べる。
質問する
社員が質問をしてきた時に本人としてどう思うか聞いてみるのは、日常業務の中で経営者の考え方を伝えるのに良い機会となる。聞いてきた社員は答えを知りたがっている状態なので、この時点での浸透効果は極めて高い。社員が「どうしたら良いでしょうか?」と聞いてきた際には、まず本人の考えを聞いてみる。いきなり結論を言わずに、本人に考えさせる。その上で自分は理由と共にこう思うということを伝える。結論ではなく考え方(理念・価値基準)を伝えるように心がける。
勿論、質問してきた社員の考え方が浅いと思えば、突き返すこともあるだろう。
経営者と社員の関係性には経営者の性格や会社の成長段階が深く関わっている。殆どの場合、創業期には悠長なことを言っていられず、社長が全てを判断し、速度感を重視して経営を行う。ある程度の段階(中間管理職が必要になった段階)で、社員への接し方を改めて見直すと良いだろう。
こんなことを直ぐにできる人は誰もいないので、思わず答えを言ってしまった時は後でこっそり反省する。私も勿論話し方で反省することが多い。但し、心がけていれば少しずつ変わっていく。
褒める
褒めるほうが叱るより簡単なのは、褒めた場合は褒められたことを繰り返すだけで良いのに対して、叱られた場合には何を叱られたのか理解した上で今後のやり方を改めるとい2段階が必要なことに由来する。
ペット等、言葉を使えないものは基本的に相手の気持ちを察知して振る舞いを変えている。また、人間も言葉が使えない乳児期には字義以外の内容で理解する。社員もこれと同じである。社員は基本的に社長のことが好きだが、社長の言葉は思ったより覚えていないと考えたほうが良い。
社員は何を褒められ、何を叱られたかは覚えているので、叱るより簡単な褒めるほうを教育にはお勧めする。
勿論、叱らなければならないこともある。
経営計画発表会
経営計画は経営者と社員のコミットメント(約束)である。その為には社員がやるべきとおもっていることと経営者がやるべきと思っていることがしっかり関連していることが必要である。即ち、経営者の経営方針を踏まえた社内各部署の計画を集約し経営計画を策定する。
こうした経営計画の発表会で、経営理念について改めて述べることは、社員の関心が高いので他の機会に比べて機能する。勿論、経営者が一方的に伝える経営計画では、社員の関心度は低い。
表彰する
先程の褒めるということと同様であるが、期末に発表する方法がある。月間MVP、四半期MVP、年度MVP等、社長賞などを与えることができる。この場合、通常業務で優秀だった社員だけでなく、理念に合致する行動を取った社員も表彰することが必要である。
1対1面談
皆さんは通常業務とは別に社員と話す機会を設けているだろうか。1on1面談と書いたが、人生相談、グループ面談や昼食、飲み会でも良い。何かの機会に相手の考え方を聞き、それに沿って経営者の判断基準を述べることで、経営理念は浸透する。
社員(残念ながら管理職も)は、通常業務を大過なくこなすことに意識が向きがちである。この中には理念やVisionを振り返る時間はない。経営者として、積極的に働きかけ、理念や目標に対して、社員の意識を向けさせる働きかけが必要である。
ところで、皆さんは経営理念をどう決めているだろうか。戦略、成長性、社会貢献等を大事にするように記述しているWebサイトは多い。確かにそれらも大事である。しかし、一番大事なのは経営者本人が自らの考えで納得していることである。決め方として、会社のCSR部門に勧められて、或いはコンサルタントに勧められてというのもあるかもしれない。もしかしたら御社の経営理念が浸透しないのは、経営者であるあなたが納得していないのかもしれない。
当然のことであるが、経営者が納得し、尚且つ覚えやすい言葉でなければ、日常業務の中で社員達に伝えることはできない。
本稿では経営理念の浸透方法について記述した。皆さんの参考になれば幸いである。